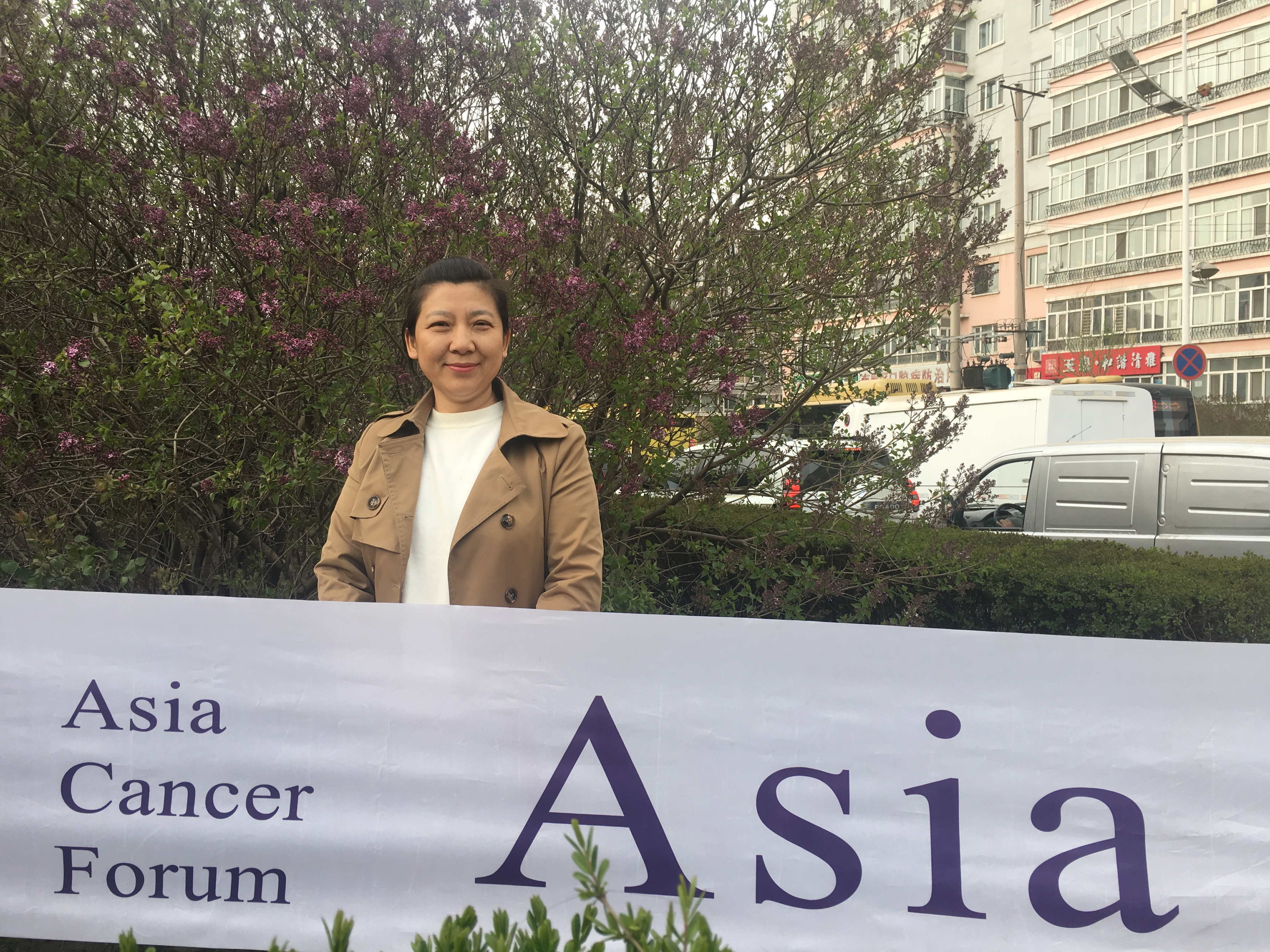コラム

-

-
過去をみつめて未来を紡ぐ
- 2019年05月28日2019:05:28:06:18:54
-
- 河原ノリエ
-
- 東京大学大学院情報学環・学際情報学府 特任講師
「葉々君為送清風」
東大でアジアの癌国際連携を研究する私の所属研究室の入り口にかかる書画は、日中国交回復の礎を作った松村謙三元厚生労働大臣が亡くなる少し前、父のために書いて送ってくださったものだ。長らく富山の私の部屋にあったこの大きな書を、財務省におられた中井徳太郎さんや、地元の老舗、日の出屋製菓のお力添えで駒場まで遠路はるばる運んでいただいた。
(写真1)
松村は、相手の境遇をよく理解してその人に一番ふさわしい言葉を選んで書を送ったひとであるということはきいていたがこれが、「禅語の虚堂録(きどうろく)」にある「衍鞏珙三禪德之國清」(衍・鞏・珙の三禅徳、国清にゆく)「「誰知三隱寂寥中。因話尋盟別鷲峰。相送當門有脩竹。為君葉葉起清風。」(誰か知らん三隠寂寥の中、話に因って盟を尋いで鷲峰に別れんとす。相送って門に当たれば脩竹あり、君が為に葉々清風を起こす。)を下敷きに書かれた書であることは、NPO法人健康医療開発機構の上田真理さんの知人の研究者によってはじめて知らされた。
南宋の臨済禅の虚堂和尚の住まう鷲峰庵に、法弟三人が天台山の国清寺の三隠(寒山、拾得、豊干)の遺蹟を訪れるため、別れの挨拶をしに来たときに虚堂和尚が玄関先で詠じたもの。門のところまで見送りに出てきたら、門前の竹薮の一葉一葉がさらさらと音をなして清風を送ってくれているという一節だそうだ。中国古典に精通し、当意即妙に書をしたためたという松村らしい。この書はたしか、松村が、あの戦争をとめられなかった悔恨を胸に、田中角栄の前捌きとして87歳の老体に鞭打ち、周恩来との会談のため訪中した1970年のすこし前にいただいたものだったとおもう。そのころ父は、シベリア抑留から戻り、すでに20年以上もたっているのに、未だにあの戦争から立ち直れず、近所の旅館の下足番をしながら、鉛色の弾がまだ残る右足をさすりながら、ぽつねんと西の空を眺めていることが多い人だった。旅館で地元の会合があるたびに、玄関で松村を見送るのは父の仕事だったのだけれど、同じ中国に想いを持ちながら不遇の人生をおくっていた父に、いつも声をかけてくださっていたという。そんな父を世捨て人のように庵で暮らす虚堂和尚に見立てて、書いてくださったのだろうか。
この書の右端の字には、私が12歳のときにペン立てを投げつけ、破けた跡がある。小学生の私にとって、松村謙三も、日中国交もあの戦争も、そしてあの家に纏わるすべてが疎ましかった。
あの家とは、父がシベリアからもどったとき、満蒙権益のうえに築いた幻のような財産の中でたったひとつ残っていた別荘。父が白頭山麓で金日成率いるバルチザンたちと闘った関東軍とともに民間人として戦時物資の供給をしていたころに建てたものだ。象牙の彫り物、熊の毛皮、中国伝来の壺、満蒙の権益の上にあったとおもわれる趣味のよろしくないものが有象無象にあった家である。その家で、あの戦争を引き摺り、ずっと立ち上がれずに世捨て人のように生き延びた父。56歳にしてはじめてできた娘が生後間もなく顔半分にやけどをして左目の視力を失ったとき、自分の中国戦線でしたことの報いだと思い悩んでいた。母は母で、事故が父の姉の不注意だったゆえ、家庭の中は、親戚が出入りするたびに、諍いがたえず、あの家の中で起きた子供時代の思い出は、思い出したくないことばかり。
私は、激しく、そうしたすべてを憎み、12歳のとき「こんな家にはいたくない」
そう言い放ち、富山大学の付属中学校に下宿して通い始めた。
大学から東京に出て、移植手術をした。化粧をしてすべてが覆い隠せるはずはなかったが、手術によって、アッカンベーした左目の下のめくれがなくなったことは大きかった。ひとから視線を慌てて外されることもなくなり、私は別の人生を生きようと思った。結婚して、すべてを忘れて生きていくはずだった。
そして、昭和は遠い日々となり、21年前双子の子を妊娠した。父の葬儀のとき、母と言い争った。どこまでも父や親族と距離を置こうとする私を執念深いとなじった母。一方的に母に切られた電話によって、昭和の家族の歴史も、この国の歴史もすべてが絡みついているような重いものと、ようやく縁が切れる、そうおもった。
しかしその後、切迫早産となり、私は23週の未熟児を生むことになる。体重がなかなか500グラムを超えず、重度障害も宣告された。私は母に、過去の逃れられないもののせいでお母さんと喧嘩してこんな子を産んでしまうことになったと、どこにもぶつけようのない苦しみをぶつけた。母は電話の向こうで声をあげて泣いた。
この子たちを抱えどう生きようかと考えあぐねた苦難の日々は果てしなく続くかにみえた。子どもたちが3歳をすぎ、新しい世紀を迎えるころ、この子たちを護るためにも、この世界の現実と向き合わなければいけないとおもった。4人の子供の母親で専業主婦で、おまけに大変な双子を抱え、あらゆる就業から拒絶されていた。でも、思ったのだ。自分とはなにかをみつめなおせば、必ず道は開けると。いろいろな方たちのご縁で、私は、世の中に出ていくことができた。いっとき、立つこともできないといわれた子たちは、なんとか小学1年生となった。そのとき、ふと、過去を恨んでいきることにすこし疲れた気がした。
父がわたしの顔の傷が自分の戦地の報いだと思った中国のその地にたってみたい。そうおもったのだ。そしてその地であった老婆に、「生き延びることがなにより大事」そう教えてもらった。「あなたがなんでもいいから、この国と日本との間でなかよくなれることひとつでもみつけてね。そしたら、私たち家族の暗い歴史もわすれる。だからあなたも忘れよう。そしたら、あなたももうすこし楽にいきられる」そう私の頬をさわって告げられた。
そのころは、中国には、戦地に謝罪の旅をして慰霊碑を立てて、戦時の日本軍の残虐さと戦争責任を声高に語る人たちが、たくさんいらしたころである。「ああいうひとは、いまの私たちのくらしにはなにも興味をもたない。自己満足に酔っているようにしかみえない。慰霊碑なんかここに立てられたら、企業誘致もできなくなる」そう呟く現地の人たちの言葉で、わたしのやるべきことを探す気持ちは定まっていった。
子供たちの苦難は続いてはいたけれど、それはもうわたしの力ではどうすることもできなくて、わたしはただ、中国と日本の架け橋になれること探そうそう気持ちが動いていった。
どんなことがあっても、自分のやるべきことをして生き延びていれば、必ずいい日は巡ってくる。そう私に教えてくれた南京の老婆の言葉をたよりに。
ちょうど、第1次安倍内閣のころ、安倍温家宝会談の軸のひとつとして、日中医学構想のひとつとしてがん医療をという話が立ち上がり、アジアゲートウェー構想を推進しておられた根本匠先生のところの方が、当時書いていた中央公論の記事をみつけて、自民党本部に呼んでくださった。2007年はじめのことである。私は、「中国と一緒にやることは、短期で取り組む感染症のような課題ではなく、なかなか先の見えない長期戦にもちこめるネタでやっていただきたい。そして何よりも、あの戦争で帰ってこられた人もこられなかったひともみんなの想いがつまった、地下の軍歴簿のうえにある厚労省の仕事として日中の癌研究を推進してほしい」そんな個人的な想いをお伝えした。その後、多くの方々のご尽力で、南京で日中国交35周年事業「アジアがん情報ネットワーク会議」開催(UICC-ARO主催)の運びとなり、その繋がりが、いまの研究につながっている。
あれから10年以上の月日がながれた。令和改元を期に、平成を振り返る試みが目立ったが、これはとりもなおさず、昭和がもっと遠い日になったということだ。改元前の昭和の日に、私には、もうひとつ心残りがあった。
故郷とはずっと疎遠となっていたのだが、昨年思いがけず、小学1年生から3年生まで担任をしてくださった西野淑子先生が東大を訪ねてくださった。小学校退任後も、地元で富山弁の民話を中心とした紙芝居活動をなさっていた。84歳のご高齢にもかかわらず、昔のままの先生におもわず、「私も先生のお手伝いします」思わず、言ってしまったのだ。
もう20年以上空き家にしていた実家。疎ましく思い出したくもない場所だったから、いずれ柱一本残さず消し去ろうと心に決めながら、東京に引き取った年老いた母の気持ちを思うと解体の踏ん切りがつかなかった実家で、私は、担任の先生の富山弁の紙芝居会「がんを学ぼう」を、私が理事長をつとめる一般社団法人アジアがんフォーラムとして行うことになった。

(写真2)
あの家には帰りたくなく、父の墓参りのかわりだと自分にいいきかせ、ずっとハルビンの農村の癌医療教育の支援をおこなってきた。今回は、そのJICA活動として制作した癌教育教材をすべて日本語、富山弁にして地域のひとたちに先生の語り口調で紙芝居でおこなってもらう会とした。方言というローカル言語による顔の見える関係性の豊かさが紡ぐ世界のなかで、このがんという病について、地域のなかで学ぶしかけには、大きな可能性がある気がする。西野先生は、同時にふるさとに伝わる民話の紙芝居もなさった。病気は本来、生物学的にいうと他人に代替されないものだが、民話の世界では、あたかも地域の自然や関係性のなかでかわりに分け持ち癒されていくものだと、医療人類学の波平恵美子先生から学んだ。まさに地域包括ケアの理念が、民話の世界にのこっていて、人々の口伝えに残っているのだ。
(写真3)
地域包括ケアなどと声高に叫ばれ、がん医療の均てん化などといわれてきたが、実際のところは大きく違う。東京や学会の上澄みの議論しかみてこないで、国際の政策研究に携わってきた我が身にとって、思いがけない学びがたくさんあった。がん医療の進歩により、入院期間が短くなり、在宅や地域でがん患者さんがすごす時間が長くなってきている。日本の医療はずっと病院医療に邁進してきたなか、今更地域のつながりといったところで、なかなか難しいものだ。自宅でひとは亡くなっていた時代は、地域のなかに、病が開かれていたにだが、いまは、それぞれの家庭のなかに、病は閉じている。そうしたなか、病院と自宅をつなぐ、中間のような場所でひととひとが繋がりをもつことを本当に探すことが必要な時代となっている。
ハルビンにおけるJICAの草の根支援活動とは、地域住民主体のがんについての学びを立ち上げることだったのであるが、こうした国際開発のスキームが、地方創生に繋がるやもしれないことを今回本当に気づかされた。そして、このがんを学ぶという地域の集まりに、この地域の癌地域連携拠点病院である地元砺波市立病院副院長が参加くださった。思いがけなく、私がずっとJICAで活動してきたハルビン市とは、地元砺波市立病院が医学交流を1980年代から続けていたという。
この地域には、中国の満州地域とのつながりがずっとあったからであろう。
飛騨山系から流れる庄川の流送技術を満州で広げるため父も多くの地元の若者を連れていき、帰れなかったひともいた。その悔恨の戦後の日々だった。
今年こそ解体をせねばと思いながら20年も空き家になっていた実家は、時折風をいれていただいて、近所の方のご厚意で、昔のままでのこっていた。
(写真4)
直前のお誘いだったのだが、地元の北陸コカ・コーラボトリングと日の出屋製菓さんもご協力をくださった。働き方改革がさけばれる今、従業員へのがん対策という企業の在り方も問われてきている。まだまだ地方にはそうした流れは届いてはいない。企業にとっては、今後投資家の眼差しにも関わる問題であり、こうした地元の優良企業が、がんを地域で学ぶ活動にかかわってくださることに、今後につながるものを感じた。
今回ずっとかかわってきた中国ハルビンのひとたちに、昭和の日のイベントを開催することを伝えたところ、市の公式花であるライラック(リラ)を実家にうえてほしいといわれ、地元の人たちと記念植樹をした。父は満州で、ハルビンから少し離れた牡丹江の駅前に関東軍御用達のホテルも経営していて、「花屋ホテル」という名前だったという。
(写真5)
(写真6)
7本植えたリラは、いまを盛りに咲いている。「リラの木の家」にしようかと地元のひとたちが、散歩コースにして水やりをしてくださっているという。
人生100年時代といわれ、がんは誰にでもかかる普通の病気になった。がんはひとに、人生そのものを問いかける病気だ。リカレント教育という言葉が最近よくきかれるが、がんという病を軸に、さまざまな角度から人生を問い直す学びを地域の中で広げていくこと、そしてそのための人の共感できる場をつくることそれが必要かもしれない。
松村謙三が最後まで気かけた中国はこの10年すごい勢いで変貌している。
「上海、北京、重慶で30万人のデータを集めることはすぐできる、AI−メディカルは中国がリードして、アジアの先端医療は中国の時代である」これは、最近中国でおこなわれたがんの国際学会で述べられた言葉だという。AIが医療の中核になるには、様々な基盤が必要であることはいうまでもないが、中国が思い描くような世界が到来することは難しいだろう。なによりも、未だに、中国の癌医療特に中国の農村部においては日本の力を必要としている。
そして、戦後74年目のいま、過去をみつめて未来を紡ぐということは何なのか、松村謙三が、戦後の長い時間を蹲るようにしてこの国の高度経済成長をただじっと見上げていた父のためにと、書いてくれた書を、毎朝、研究室の入り口でみながら、わたしは考え続けている。
【参考文献】
中央法規出版社 河原ノリエ 恋するように子育てしよう!
春秋社 河原ノリエ いのちのかなしみ
---
河原ノリエ(東京大学大学院情報学環・学際情報学府 特任講師)