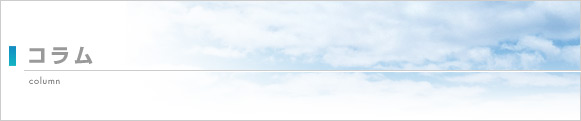(掲載日 2005.2.15)
かねてから「崇め」ている雑誌がある。「ニューヨーカー」である。アールデコ風のタイトル・ロゴといい、ソール・スタインバーグの表紙イラストといい、内心ひそかに目標としている雑誌のひとつである。クオリティペーパー(高級誌)として英国の「エコノミスト」を褒める人は珍しくないが、志の高さでは「ニューヨーカー」のほうが上だろう。日本の出版界の志の低さを見るにつけ、この妥協のない質には感嘆するほかない。■医療現場の矛盾を暴く ■告げられなかった「失敗」
javascriptの使用をonにしてリロードしてください。
メニューの表示にはjavascriptを使用しています。